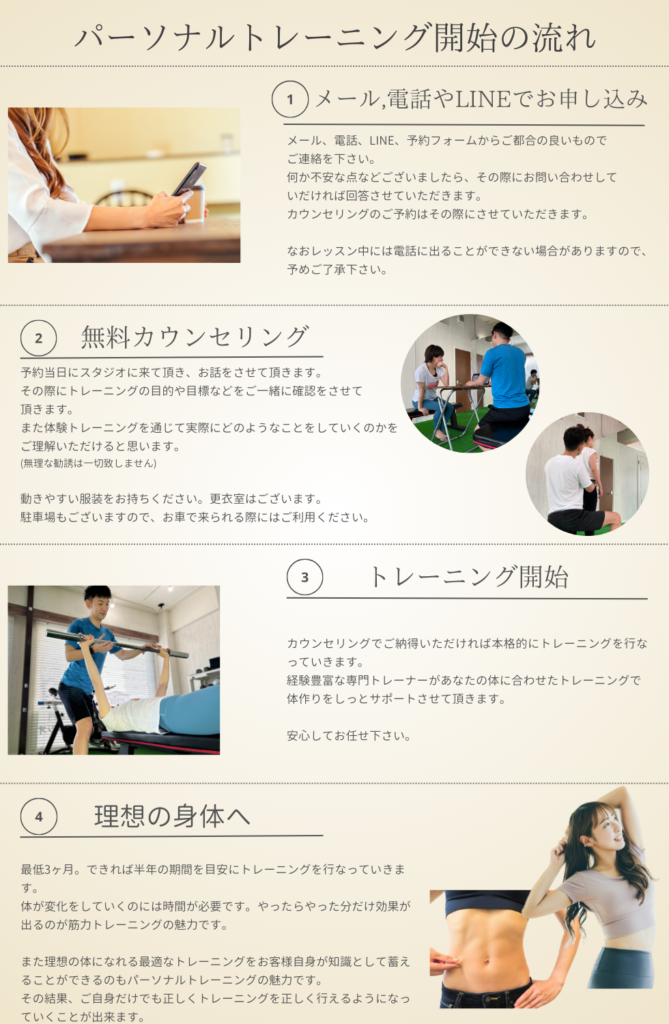こんにちは。御影にあるパーソナルトレーニングスタジオFitness fieldの前田です。
肩周りを動かそう
パソコン仕事をされる方に多い肩周りの不調。首がカチコチになっていたり、
こういう横に広げる動作で既に痛いって言われる方、結構いらっしゃいます。
外旋という動きですが、この写真でも脇が空いていますが、閉じることが出来ない。とも言われます。

スタートポジションは脇も閉じていますが、横に広げると脇が空いてしまう。
肩甲骨の動きが悪かったり、姿勢が悪かったりすると上手く外旋ができない。っていうことはよく起こります。
そして、同時に肩が凝っている感じがする。とも言われます。
肩周りの可動性はとても重要。そして繊細です。股関節よりも圧倒的に繊細な部位だと感じています。
基本的なトレーニング。ベンチプレスやローイングなど普通の筋力トレーニングを行う場合でも肩周りの可動性を良い状態に持っていかずに行うことで、関節にとってストレスがある動きになってしまい、続けていくとどこかしらに不調がやってくるという残念な結果になることがよく起こります。
それはとても残念ですし、たまに言われるのが、筋トレすると体が痛くなる。体が硬くなる。っていう誤解をなんとかしたいとも思っています。
準備運動としての動的ストレッチは色々なバリエーションがありますが、実際にパーソナルトレーニングのセッションで行う場合には人によってかなり変更を加えていきます。
お客様の体には左右差があることも多いですし、続けていくことで危険がある場合には筋力トレーニングを行っていても途中でも動的ストレッチに変える場合もあります。
トレーニングの原則の中に安全性。というものがあります。これって蔑ろにしてはいけなくて、むしろ一番重要視しないといけない部分です。
安全である。当たり前すぎることですが、一番重要なんです。
その安全性をより高めるために可動域が充分にあることは1つのポイントになります。
可動制限があることも考えてはいます。(怪我などで動かない場合も考えられます)その方が持っている可動域をしっかりと見極めながら、そして左右のバランスを整えながらトレーニングを進めていくものです。
その上で肩周りを動かそう。っていうことにもどっていきます。
軽いディップス pic.twitter.com/KpM768TWAC
— 前田@fitnessfield (@fitnessfield2) July 11, 2021
上からバネで肩周りを強制的に動かしています。バネの力は強くないのですが、上手く脱力することで自然と上に上がっていきます。そして可動域が一番多いところまで動かしていくことができます。これだけが全てではありませんが、肩周りをしっかりと動かすスタートになります。肩甲骨がとってもよく動きます。
胸の可動域を広げる pic.twitter.com/6sDQQPAYKC
— 前田@fitnessfield (@fitnessfield2) July 11, 2021
今度は胸のストレッチです。肘がなるべく後ろに下がることで胸(大胸筋)がストレッチされます。そして同時に肩甲骨が内転(背骨側に寄る)します。肩甲骨はしっかりと動かされて、胸がしっかりと伸びている状態を作ることができます。見た目はチェストプレスですが、鍛えている感じはなくて(バネの強さが弱い)伸ばされる意識をとても持っています。
この2つをかなりの回数を行うことで肩周りは緩んできます。そしてその上で筋力トレーニングを行えば、安全でそして可動域がしっかりとある状態を作ることができます。そして痛くもならないです。(筋肉がパンパンになって痛いことは含んでいませんが、、、)
肩周り緩ませることはとっても大切ですよ。